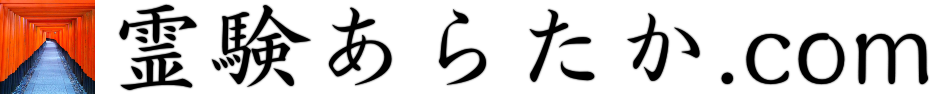この体験談は、神奈川県在住の看護師、ゆかりさん(32歳・女性)から寄せられたものである。彼女の話を聞いたのは、初夏の穏やかな午後のことだった。カフェの窓際の席で、ゆかりさんは時折言葉を選びながら、慎重に当時のことを語ってくれた。
事の起こりは昨年の十一月、ちょうど冬の訪れを感じ始めた頃のことだという。
ゆかりさんは総合病院の外科病棟に勤務している。夜勤が月に八回ほどあり、その日も夜勤明けで自宅に帰る途中だった。朝の七時過ぎ、まだ薄暗い空の下、いつもの駅からバスに乗った。
疲れ切っていた。前日は緊急手術が二件入り、ほとんど座る暇もなかった。バスの座席に身を沈めると、意識が遠のいていくのがわかった。「次の停留所で降りなきゃ」と思いながら、気づけば眠り込んでいた。
目が覚めたのは、終点のバス停だった。
運転手に起こされ、慌てて降りたゆかりさんは、そこが見知らぬ場所だと気づいた。山間部の小さな集落。周囲に人の気配はなく、店も何もない。スマートフォンを取り出すと、圏外の表示が出ていた。
「その時初めて、本気で焦りました」とゆかりさんは言う。
バスは折り返して行ってしまった。次のバスまで三時間以上ある。歩いて戻ろうにも、どちらの方向に進めばいいのかもわからない。曇り空の下、気温も下がってきていた。ナースシューズは歩きやすいが、長距離を歩くには向いていない。
途方に暮れて道端に座り込んだ時、ふと制服のポケットに手を入れた。そこに、小さなお守りがあることを思い出したのだ。
それは三年前に亡くなった祖母の形見だった。祖母が生前、いつも大切に持ち歩いていたお守り。「これはね、お伊勢さんでいただいたものなの」と、祖母は何度も話していた。葬儀の後、形見分けの時に母から渡され、ゆかりさんはずっと制服のポケットに入れていた。
正直、お守りの効果を信じていたわけではなかった。ただ、祖母を身近に感じられるから持っていた。それだけだった。
でも、その時。手のひらの中の小さなお守りを握りしめながら、ゆかりさんは自然と祈っていた。「おばあちゃん、助けて」と。
どれくらいそうしていただろうか。遠くからエンジン音が聞こえてきた。
軽トラックが一台、ゆっくりとこちらに近づいてくる。運転席には七十代くらいの男性が座っていた。トラックはゆかりさんの前で止まり、窓が開いた。
「どうしたんだね、こんなところで」
事情を説明すると、男性は「それは大変だ」と言って、駅まで送ってくれることになった。車内で男性は、この辺りは携帯の電波が入らないこと、バスで寝過ごす人が時々いることなどを話してくれた。
「でもね、普段この時間にここを通ることはないんだよ。今日はたまたま、朝早く用事があってね」
その言葉に、ゆかりさんは胸が熱くなったという。
駅まで送ってもらい、何度もお礼を言って別れた。改札を通る時、もう一度ポケットのお守りに手を触れた。不思議なことに、いつもより温かく感じた。
「おばあちゃんが、あの人を向かわせてくれたんだと思います」
ゆかりさんはそう言って、カップのコーヒーを一口飲んだ。その表情には、確信があった。
その後、ゆかりさんはお伊勢参りに行くことを決めたという。祖母がいただいたお守りに、自分自身もきちんとお礼を伝えたいと思ったからだ。年明けに休暇を取り、三重まで足を運んだ。
「内宮で参拝した時、涙が止まらなくなって。周りの人に変な目で見られたと思います」
何に対する涙だったのか、ゆかりさん自身もうまく説明できないと言う。ただ、祖母への感謝、助けてくれた男性への感謝、そして自分が無事だったことへの安堵。それらがすべて混ざり合った涙だった。
今もゆかりさんは、あのお守りを制服のポケットに入れている。新しくお守りもいただいてきたが、祖母の形見は別格なのだという。
「お守りって、ただの布と糸でできているんですよね。でも、その中には確かに何かが宿っているんだと思います。それが神様なのか、持ち主の想いなのか、わからないですけど」
ゆかりさんの言葉は、私の心にも深く響いた。
形見として受け継がれるお守り。それは単なる物ではなく、人と人とをつなぐ目に見えない糸なのかもしれない。そして、本当に助けが必要な時、その糸は強い力を持って私たちを守ってくれる。
話を終えたゆかりさんは、「こんな話、誰にも信じてもらえないかもしれませんね」と照れくさそうに笑った。いや、信じる人は必ずいる。そして何より、その体験はゆかりさん自身の中で確かな事実として存在している。それで十分なのだと、私は思った。
お守りの持つ力。それは時に、私たちの想像を超える形で現れるのかもしれない。